ナット止めハブのクイック化 |
|||||||||||||||||||||
|
昔のハブはすべてナット止めでしたが、70年代に入ってクイックレリースで止める方法が出てきました。パンク修理や輪行時のホイール着脱がすばやく出来るためランドナーを中心に増えてきて、現在では中級クラス以上のサイクリング車はすべてクイック使用ですが、一般車や子供用車はナット止めが主流です。時々ハブのクイック化について聞かれますので、まとめてみました |
|||||||||||||||||||||
フレーム形状 |
|||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||
|
ハブをクイック化にするにあたり、フレーム本体がクイック化に適応しているかが最初で最大の問題となります。ナット式ハブはフレームをナットで挟み込む構造なので本体の受け部分の厚さは問題になりません。しかし、クイック式ではハブシャフトの上にフレームが乗っかる構造になり、乗っかる部分の厚さ(5mm以上)が必要になります。また、シャフト端についたクイック機構によってはさみこむ構造になっているので、シャフトはエンドから出てはいけません。
|
|||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||
|
一般車によく採用されている先が細くなっているプレスエンド(左)はクイック化はしません。またハブ軸にディレーラーブラケットやディレーラーガードを挟み込んでいる物(中)、キャリヤエンドやスタンドを挟み込んでいる物(右)も、ハブ軸がエンドより外に出ないと言う構造上の問題で使用できません。ブラケットやガードの厚み分だけシャフトを延長すれば乗せる事は可能でしょうが、クイックを外した時にディレーラーやガードがハブと共に外れてきますので、クイックの意味合いが薄れてしまいますね(笑)。
|
|||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||
|
上記でプレスエンドに対してクイック化は「出来ません」ではなくて「しません」としたのには訳があります。プレスエンドの厚さは4mm程度のものが多く、2mmのハブワッシャ(写真での黄色パーツ)をあわせると6mm程度になってクイック用エンドと同じ厚さになりますのでクイック化できそうに見えます。ハブワッシャの名称は「前輪脱輪防止用舌付きワッシャ」と言いまして、前輪が下方に抜け落ちるのを防ぐ役割をしています。クイック用エンドには付いていないのでクイック化での前輪脱落は問題ないように思いますが、聞いた話では、鍛造のクイックエンドに比べるとプレスエンドは変形しやすいので、緩んでも脱落しないように付いているのだそうです。しかし、昔のプレスエンドには無かったそうですし、クイック化してもきつく締めこんでおけば問題無さそうですが、ワッシャを挟んでいますのでズレの発生も考えられ、条件的には不利だと思います。また、クイックを緩めるだけでは舌付きワッシャの掛かりが取れなくてナットを緩める事になり、クイックの利点がなくなると共に、再度の締付を注意深くしないと締付不足の発生が予想されます。プレスエンドをクイック化している人をNetで見かけますが、実施される場合は走行前の念入りな確認をお勧めします。私なら・・・、素直にナット止めにしておきます。
|
|||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||
|
リヤに関してはチェーン引きが必要なエンドには使用しません(使用してもクイックの利点がほとんどありませんね)。ストレートドロップアウトエンド(ストドロエンド)やロードエンドは、エンドの厚さが5mm(DuraAceは6mm)以上有れば使用可能です。クイック化を考える前に、自転車のフレームをよく確認してください。
|
|||||||||||||||||||||
オーバーロックナット寸法 |
|||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||
|
フレームがクイック化可能とわかれば、次はオーバーロックナット寸法(O.L.D.:詳細はリンク参照)の測定です。フロントは100mm、リヤは5段が120mm、6段が126mm、7段以上が130mmか135mmが多いですが、フロント96mmやリヤ124mmなどのものもあります。
|
|||||||||||||||||||||
ホイール交換 |
|||||||||||||||||||||
 |
最近は完組みのホイールが売られていますので、O.L.Dとリム・タイヤサイズが合えばフロントならそのままポン付け可能です。リヤはINDEXなど汎用性の低い変速システムでしたら同じ仕様のものが必要になりますが、旧来のフリクション式変速ならO.L.Dと段数さえあえばポン付けできそうです。 |
||||||||||||||||||||
シャフト交換 |
|||||||||||||||||||||
 |
ホイール交換はコストがかかりますので、安く仕上がるシャフト交換は魅力的ですが、条件も限られてきます。まずはハブの製造会社と製品名を確認しましょう。ただし、最近の製品は番号が本体に明記されていますが、普及グレードや昔のハブは社名くらいしか書いてなく、製品名不明のことがよくあります。 |
||||||||||||||||||||
同じ製品でナット止めとクイック止めの両方の製品が出ている場合 |
|||||||||||||||||||||
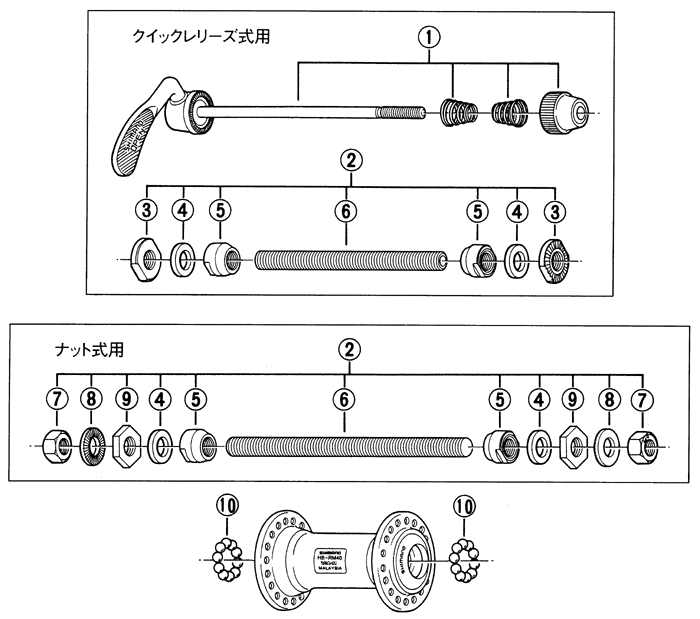 |
|||||||||||||||||||||
|
これが一番ラッキーで安上がりな場合で、シャフト交換でクイック化できます。シマノのHB-RM40を例にとってみますと、⑥番のシャフトをソリッドから中空へ軸交換すれば出来上がりです。⑤の球押しと④の調整座金は流用できますが③のロックナットが必要になりますので、実際には②のハブ軸組立品(Y21H98050、\1,200)を購入するのがお徳で確実です。
|
|||||||||||||||||||||
ナット止めの製品しかない場合 |
|||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||
|
ハブシャフトにはインチネジの5/16・3/8と、ミリネジのM9・M10の2種類が存在します(リンク参照)。国産中空シャフトはミリネジのみですが、ナット止め用のソリッドシャフトは2種類の製品が出ています。まずは自分のシャフトのネジ径を調べるのですが、簡易的にはノギスなどで測るしかありません。ナット止めハブの場合、ミリネジのソリッドシャフトを使用しているのは一部のMTBやトラックなど特殊な車両しかなく、ほとんどの一般車はインチネジのソリッドシャフトを採用していますので、クイック化計画もすんなりと行かない方が多そうです。 |
|||||||||||||||||||||
シャフト径がミリネジ(M9・M10)の場合 |
|||||||||||||||||||||
 |
ハブのO.L.D.に合った長さの中空シャフトを購入して組みかえるだけでOKです。国産中空シャフトは材質の違いはあれど規格は共通ですので、他社製品を使用しても問題ありません。O.L.D.に+8~+11mmを加えた長さの中空軸を選ぶので、O.L.D.126mmなら137mm、130mmなら141mmの中空シャフトになります。球押しとワッシャ、ロックナットは流用できます。ただ、ナット止めなのにインチネジを使わずにミリネジを使う意味が完成車においてあるのかどうか、共用部品のコストカットとしても、あまり見かけるものではないと思います。 |
||||||||||||||||||||
シャフト径がインチネジ(5/16・3/8)の場合 |
|||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||
|
ミリネジと同じように中空軸に交換すればよいのでしょうが、インチネジの中空軸製品は国産には無くて、中華製のものを海外から取り寄せになるようです。結局、インチネジ用の本体にミリネジのクイック用中空シャフトを使用するわけですが、2種のシャフト径は0.5mm程度しか違わないのでミリネジシャフトがハブ本体につかえることは滅多にありません。
|
|||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||
|
同一会社の違うモデルから玉押しを調達してクイック化することは時として可能です(リンク参照 シマノ・SUNSIN)。ただし、どのモデルにどの製品が適合するかの情報は製造会社ですら持っていないと思われ、トライアンドエラーで使用出来ても、自己責任の範疇を越えない使用法になると思ってください。
|
|||||||||||||||||||||
クイックリリースの調達 |
|||||||||||||||||||||
|
クイックリリースのシャフト径は共通(5mm)ですので社外品でも良いのですが、長さは各種ありますので購入には注意してください(リンク参照)。 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||